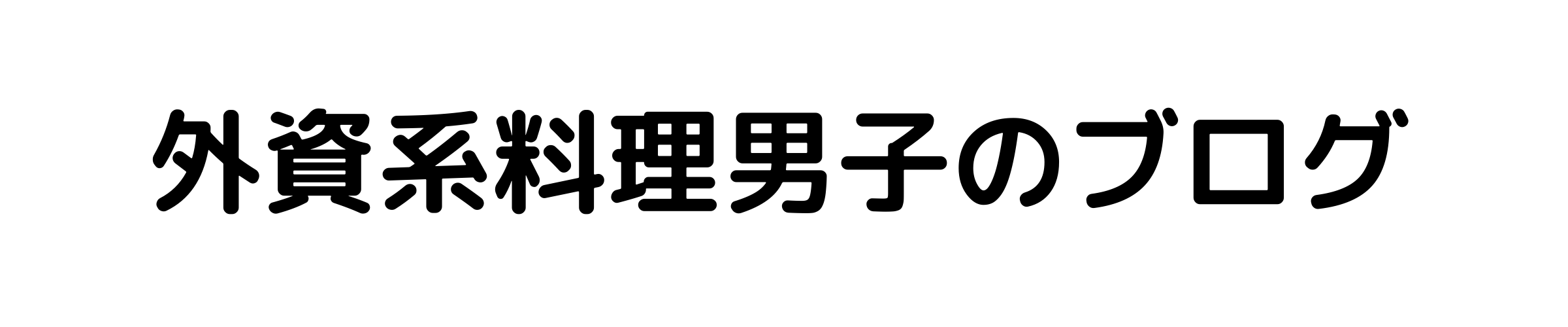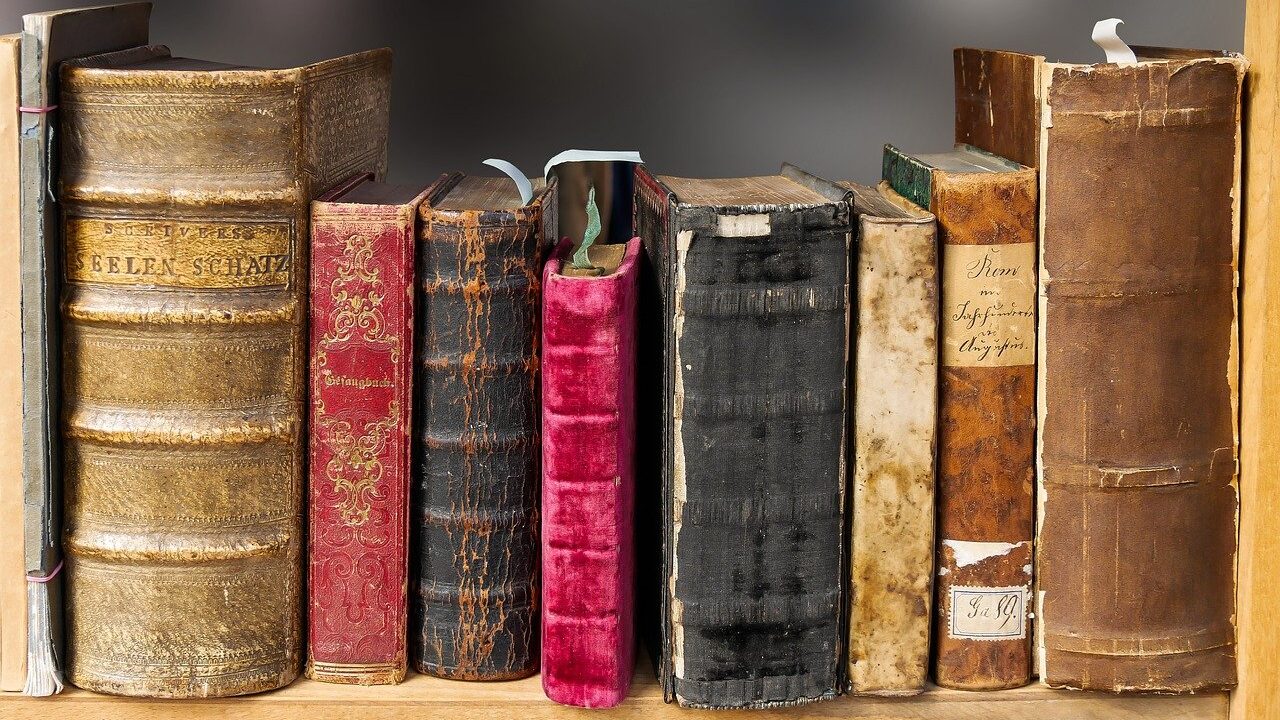「ティール組織」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
2014年にフレデリック・ラルーの著書「Reinventing Organizations」で紹介された次世代型の組織論です。
日本語では、「ティール組織」という本が出版されています(Amazonにリンク)。
筆者はこの本を読んで率直に「日本社会では機能しないな」と思いました。
その理由として、
- ティール組織は「性善説」に基づいている
- 日本に助言システムや議論による解決プロセスは向いていない
- 責任の所在があいまいになる恐れがある
などがあります。
要は営利企業に関しては各社員が組織理念に共感し、その理念のもと各社員が自ら責任とリーダーシップを持って権限行使する自主経営(セルフマネジメント)は難しい、ということです。
この記事では以下のことを考察・解説しています。
・ティール組織とは?(他の組織との違い)
・ティール組織のメリット・デメリット
・日本では機能しない理由
- あくまで筆者(20代後半)の考察です。
- 内容を要約しているので気になる方は是非原本をお読みください。
ティール組織とは?
簡単にティール組織の特徴を箇条書きにすると、以下のような従来の組織ではありえない点が多いです。
- 管理職や本部組織が存在しない
- 意思決定権者はトップではなく各社員に移譲されている
- ジョブディスクリプションがない
- 目標、予算、計画はチームで決める
- 自分の給与は自分で決める
- 危機が発生した際には全員で情報共有、対処される
他の組織との違い
このティール組織の著者は、以下のように色分けしています。
- レッド:力による支配的なマネジメントを行う組織。マフィアやギャング。
- アンバー:規則、役割に厳格な組織。教会や軍隊。
- オレンジ:階層構造はあるが実力主義。多国籍企業。
- グリーン:オレンジより多様性あり、権限が社員たちに移譲されている。
- ティール:組織が1つの生命体としてとらえる。
ティール組織のイメージは、
共通理念を持つ主体的な個人の集まり=生命体としての組織
と筆者は理解しています。
本来の一般的な企業では、オレンジ、グリーンのように、主任、課長、部長、役員、社長という階級構造から成り立ち、重要な意思決定も上記のレポートラインによって行われる。
また、社員はもっぱら「給料を得るために労働力」を提供しており、役職に見合った権限や責任のもと仕事をしている。
一方、ティールの組織では、
- 部品発注、受注などは個人またはチーム内の裁量のもとに決定される
- 問題が発生すれば上席の報告なしに自ら考えて対処する
- 働くことは単なる労働力ではなく、組織の存在意義に基づき価値を提供している。
③に関してオランダの地域介護組織のビュートゾルフで働く職員は、
労働を単なる給料を得る手段というよりも、「患者の幸福」のためと考えているようです。
つまり、患者が幸せになるために、どうしたらいいのか、どう改善すればいいかを自主的に考え、チーム内で相談し、実行するというプロセスを行っています。
職員の共通理念に基づく自主的な行動には、管理をするマネージャーや統制する本部機能も必要ありません。
なぜティール組織が成り立つのか?
上記のビュートゾルフの例をみて、疑問に思った方もいると思います。
- 権限を悪用する人がいるのでは?サボる人がいるのでは?
- 営利企業の場合、個人の実績はどう評価されるのか?
- もしチーム内でもめごとが発生したらどうなるか?
ティール組織が成り立つ前提条件は、
・社員はちゃんと働くと信頼している(性善説)
・評価や給与はチームメンバーと話し合って決める。またサボっている人がいれば注意するのがメンバーの役目(ピア・プレッシャー)
・個人に権限が委譲されていても、(ある組織によって)助言システムという第三者のチェック機能がある(なお、助言は無視しても良い)
・もめごとは当事者間のみで解決。もしくは仲介者が介入する(派閥などによる紛争には発展しない)
まず性善説として社員は組織の存在意義に共感し、誠実に仕事をしていることに加え、同僚の目(ピア・プレッシャー)が働くことで組織の統制が取られているのだと筆者は解釈しています。
そのために採用プロセスでは、期間の長い研修期間が設けられており、「本当にこの組織と自分の理念が合っているか」を新入社員に考えてもらいます。
もし組織が合わないと考える社員には、内定辞退の際に一時金が支払われる会社の事例も紹介されています。
また、不正を行った場合は、当然解雇ですが、不正による解雇は事例として少なく、社員と組織の理念が合わなくなり、自己都合退職するケースが多いといわれています。
(同僚から退職を勧められるケースもある)
従来の組織の単純比較として、ティール組織では組織理念や存在意義に重きを置いていることがわかります。

ティール組織のメリット・デメリット
本著では、なぜ従来組織(オレンジ・グリーン)からティール組織へのパラダイムシフトを説いているのでしょうか。
それは従来の階級組織での下記のような欠点があるからです。
従来の組織構造では、
- 新しいアイディアが生まれにくい
- 社員の生産性が低い(高い組織もあるが)
- 意思決定に時間がかかる
上記の点から組織として急な変化に対応しにくくなります。
ティール組織のメリット
主に以下の3つが考えられます。
①メンバーの主体性や当事者意識が高まる
→生産性向上、新たなアイディアが生まれる
②権限が付与されており、素早い意思決定が可能
→急な変化にも対応できる
③管理部門などの本社機能が必要なくなる
→コストカット
本著では、従来組織の違いとして、
ティール組織では「ありのままの自分」をさらけ出すことができると書かれています。
確かに、筆者の会社で「好きに行動していいよ」と言われ、上司もいなかったら次の日からやりたい放題やっていると思います(笑)
ティール組織のデメリット
もうお気づきかと思いますが、デメリットは以下3点あると思います。
①自己管理できる社員でないと成り立たない
→ 生産性の低下+組織の崩壊
②リスク管理が難しい
→ 助言システムがあっても社員に権限移譲は危うい
→ 責任の所在があいまいになる可能性あり
③営利団体+大規模組織では実現しにくい
→ 理念の共有がどこまでできるのか?
(非営利・非上場ならできそう)
いくらセルフマネジメント(自己管理)の組織でも、営利団体や大規模になると難しいのではないでしょうか。
現に、本著では電力会社のAESやITコンサルのBSO/オリジンは投資家の反対もあり、ティール組織から従来型の組織経営方針に戻したとあります。

ティール組織が日本では機能しない理由
以下は筆者の考察です。
上述したデメリット②がティール組織を導入する大きな阻害要因になると考えています。
いくら「自由と責任」のもと社員に権限移譲したり、意思決定の前に助言システムを設けていても会社としてリスクを管理できないことです。
個人が責任を取れない
例えばプロジェクトを社員自身で計画して失敗し、大損失を計上した場合でも、日本の法律上、簡単に社員を解雇できないためです。
もし社員が大きなミスをしていた場合でも、会社側の教育不足という落ち度となる場合もあります。
「自由と責任」とは言いつつも、会社側にとってのリスクのほうが大きいように思えます。
助言システムが機能しない+責任の所在が不明確
ある会社の事例では、社員が意思決定を行う際には、誰かに助言をもらうという助言システムが紹介されていました。
ここでは、「こういうプロジェクトをやろうと思う」に対して、非公式にチームメンバーやCEOに助言をもらって社員本人がプロジェクト実行の意思決定を行います。
本著では、第三者の視点も入り良い制度だと思いますが、
日本では機能しないどころか、責任の所在が不明確になる恐れがあると思います。
日本企業の場合において、少なくとも年上の社員から助言をもらったら、何かしらの強い意味を持つと思います。
もしベテラン社員から「そんなの失敗する」と言われたら、やる気なくなりますし、逆に「こっちのほうが良いよ」と半ば強制させてプロジェクトを実行した場合に、失敗の責任を取りたくないですよね。
この助言システムは、年功序列がなく、若手もベテランも平等の立場であるという環境が担保されていることが前提だと思います。
よって、ティール組織はNGO組織には向いていますが、少なくとも日本の営利企業では採用できない幻の組織論なのではないかと考えています。
最後に
いかがでしたでしょうか。
本著は、とても先進的な考えで、組織論について学ぶことが多い本です。
是非、この本を読んでご自身でティール組織はどのような組織かを理解してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
2021年5月5日