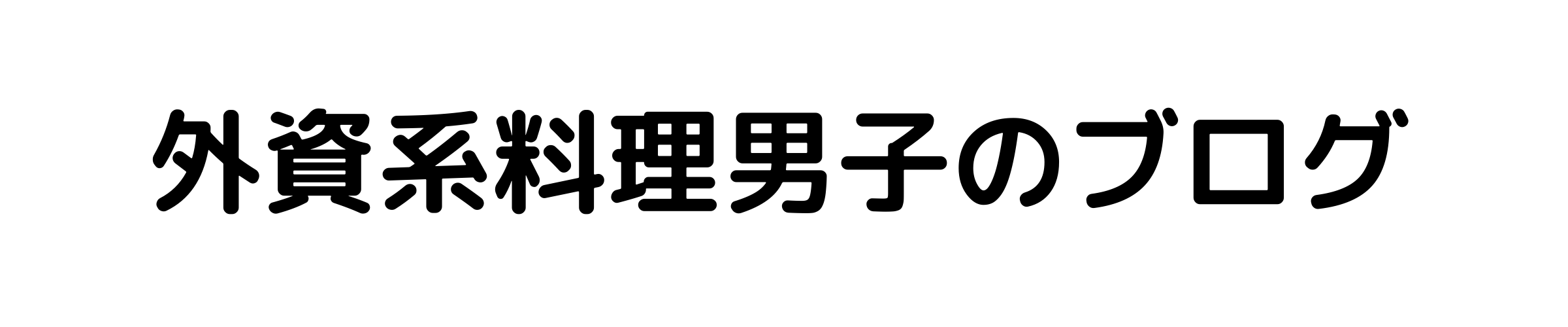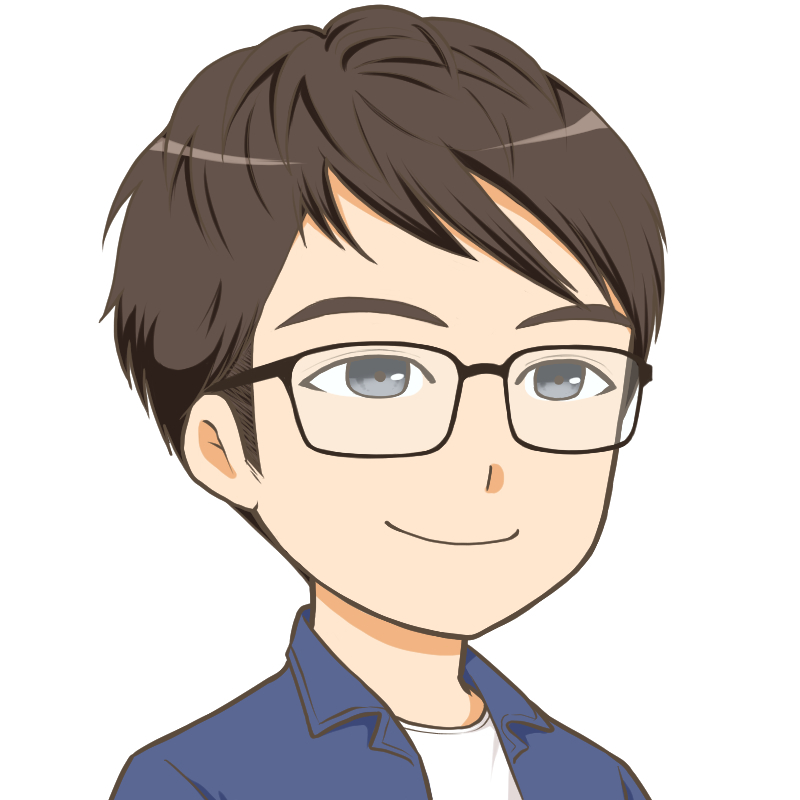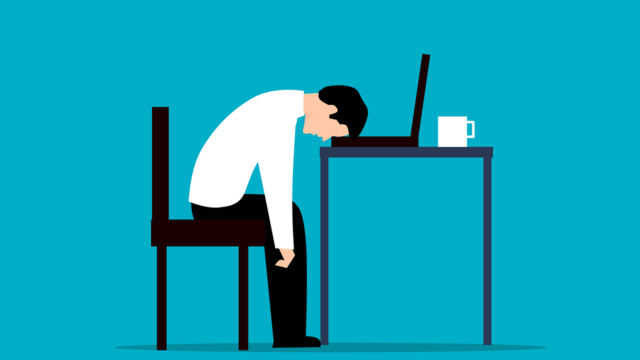昨今、日本では再エネブームを迎えています。
特に政府は2050年の脱炭素社会を目指して、再エネ電源比率の向上を掲げています。
現在の再エネ電源比率は20%弱ですが、2050年には50~60%までに引き上げるという政府案も出ています。
その再エネ電源の主役は「洋上発電」です。
でも、こんなに日本で風力発電ブームが来ているのに、
なぜ国内に風力発電機メーカーがないの????
と思いませんか?
この記事では以下のことを解説しています。
・日本でかつて風力発電機を製造していた企業
・事業撤退してしまった理由
かつての国内風力発電機メーカー3社
以下の3社が風車を製造していました。
- 三菱重工業
- 日本製鋼所
- 日立製作所
各社の参入から撤退に至るまでの経緯を調べてみました。
調べてみると、日本の風力発電の歴史は深く、三菱重工業は1980年代から発電機を製造しています。
2010年以降、上記各社は風力発電を新たな商機として開発を進めてきましたが、
- 不具合による製造中止
- 海外メーカーとの価格競争激化
- 日本の洋上風力開発(福島沖)の事業失敗
などを理由に2020年には国内発電機メーカーはなくなりました。
では、1社ずつ見ていきましょう。

日本製鋼所の風力発電機事業と撤退理由
- 2006年:製造開始
- 2010年:風車の羽部分に不具合発生
- 2013年:三重県の発電所にてブレード、ナセルが脱落
- 2016年:製造中止
- 2019年:事実上の撤退
納入実績
2006年から2016年にかけて国内で135基の納入実績があったと言われています。
撤退理由
上記のとおり、事故が原因のようです。
2013年の三重県での事故をきっかけに全国納入済風車の部品交換対応に追われ、特別損失を計上していました。
三菱重工業の風力発電機事業と撤退理由
- 1982年:日本での商用機第一号機を納入
- 1987年:北米市場に参入
- 2010年:英国にて洋上風力事業に参入
- 2014年:MHIヴェスタスを設立を発表
- 2016年:英国、ドイツ、ベルギーなどで洋上風車製造受注
- 2020年:ヴェスタスとの合弁解消。洋上風車開発から撤退
納入実績
国内外で4,200基超(約440万kW)の風力発電設備を納入。
撤退理由
一見すると好調にいっていたのになぜ?と思いますよね。
理由は以下3つが考えられます。
1つ目、三菱重工業は早々に陸上風車から洋上風車へ方向転換したこと(陸上風車の実績が乏しく、のちの洋上風車開発もうまくいかなかったため)
2つ目、MHIヴェスタスとの合弁会社についても、実際はヴェスタスの欧州工場で風車を製造しており、三菱重工業では製造ノウハウが得られなかった。
「両社で技術を持ち寄り」とのことですが、風車の基幹技術はヴェスタスに頼っていたようです。
3つ目、福島県沖の洋上風力設備の稼働率があがらず、経済産業省の実証実験がうまくいかなかったため。
ちなみ、3つ目の裏事情としては、下記のような業界環境の変化も影響しています。
- 新型コロナによるボーイングの航空機体部品の需要激減
- 環境配慮により石炭火力発電設備に逆風
- MRJ(元MSJ)開発の実質中止
陸上風力に関しては、2008年から米国でGEと特許訴訟を繰り返し、2013年に同社と和解したあと、北米の陸上風力は撤退しています。

日立製作所の風力発電機事業と撤退理由
- 2011年:茨城県に風力発電機製造工場を新設
- 2012年:富士重工業(現SUBARU)から風力発電事業を買収
- 2015年:国内最大級の大型風力発電機を完成
- 2018年:台湾で初の洋上風力発電機の受注
- 2019年:自社生産を中止、提携先の独エネルコン風車に一本化
納入実績
2016年には新規設置の国内シェア(台数ベース)は約4割を占めるなど、少なくとも国内ではかなりの納入実績があったようです。
2MWクラスでは日立製が多いのではないでしょうか。
撤退理由
理由は以下3つが考えられます。
1つ目、2014年からGEなどの海外メーカーが国内市場に参入してきたこと。
2つ目、2019年に発電事業者の再編があり、風車製造メーカーに対する価格抑制圧力が更に強くなった
3つ目、現在日立製作所は「ルマーダ」というIoT事業に注力しており、風車製造ではなく、デジタル技術を活用した風車の保守・運営サービスで収益力を高めたいという思惑があったこと。
また、三菱重工業と同様に、福島県沖の実証実験失敗の影響もあるかもしれません。
【考察】日本企業が風車製造が難しいワケ
以下はあくまで筆者の考察です。
日本企業には「風車製造に向かない事情」があると思います。
- 風車は部品数が多いこと(=低コストの調達が必要)
- 日本の独特な地形の問題(=技術革新が進まない)
風車の部品数が多いこと
風車には約1万5千のパーツが必要と言われています。
中国の風車メーカーは安価に部品調達することで高い価格競争力を保っています
三菱重工業もかつて2010年代ごろに中国メーカーに製造技術供与をしていました。これは、技術供与して中国で作ってもらったほうが安価で済むと考えたからでしょう。
日本の独特な地形の問題
日本には陸上風力向きの平坦な土地が少なく、洋上風力向きの遠浅の海辺が少ないです。
よって、洋上風力では2012年から福島沖の浮体式の実証実験を行っていましたが、失敗に終わり、企業として洋上風力事業の道筋が見通せなくなりました。
最後に
いかがでしたでしょうか。
私も気になって調べてみましたが、撤退には様々な要因がありました。
今後、政府として洋上風力を推進していくならば、海外メーカー(特に中国)に頼っていくことになるでしょう。
風力発電が基幹産業となりつつある昨今、日本国内に風車メーカーが1つもないことは今後の国の課題になるのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
2021年4月21日更新